2013年11月01日
稲城の宝「大丸用水」遊歩道を歩く~大丸用水(稲城市)~
10月26日(土)は、三多摩エンジョイ倶楽部のイベントで、
稲城市を散策してきました。
台風27号の影響も懸念されましたが、
集合が午後だったこともあり、
当初は雨の降る中での散策になりましたが、
無事行なう事ができました♪
JR南多摩駅から散策のスタートです。
まずは、稲城の宝!とまで言われる「大丸用水」沿いの散歩道です。
実は個人的には、2年ぶりの来訪になります。
26日当日は雨だったこともあり、写真をなかなか撮れなかったので、
その2年前に撮った写真をどうぞ♪

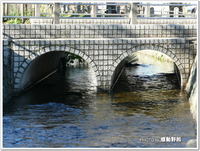

この遊歩道沿いの一般家庭では、
ガーデニングで彩りを添えているお宅や、
西洋もののオブジェが並んでいるお宅があり、
また日本庭園をモチーフにしたような小さな公園や、
田園風景も広がっていて、
晴れた日に散策するには、最高の遊歩道ですよ。
*****
大丸用水は、単なる景観用水としてだけではなく、
江戸時代初期から現在まで約400年に渡って、
農業用水として利用されています。
*****
大丸用水
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
稲城市を散策してきました。
台風27号の影響も懸念されましたが、
集合が午後だったこともあり、
当初は雨の降る中での散策になりましたが、
無事行なう事ができました♪
JR南多摩駅から散策のスタートです。
まずは、稲城の宝!とまで言われる「大丸用水」沿いの散歩道です。
実は個人的には、2年ぶりの来訪になります。
26日当日は雨だったこともあり、写真をなかなか撮れなかったので、
その2年前に撮った写真をどうぞ♪

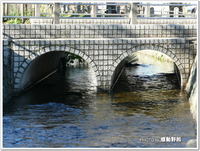

この遊歩道沿いの一般家庭では、
ガーデニングで彩りを添えているお宅や、
西洋もののオブジェが並んでいるお宅があり、
また日本庭園をモチーフにしたような小さな公園や、
田園風景も広がっていて、
晴れた日に散策するには、最高の遊歩道ですよ。
*****
大丸用水は、単なる景観用水としてだけではなく、
江戸時代初期から現在まで約400年に渡って、
農業用水として利用されています。
*****
大丸用水
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
2013年11月01日
多磨八座のひとつ~青渭神社(稲城市)~
10月26日(土)は、三多摩エンジョイ倶楽部のイベントで、
稲城市を散策してきました。
大丸用水遊歩道を歩いたのち、訪れたのが、
「青渭神社(あおいじんじゃ)です。

現在の社殿は(昭和49年)に造営された
コンクリート造りであるが、
覆殿内に安置された本殿は17世紀初期の建立と推測されている。
境内は、天気のせいもあるかもしれませんが、
静かで心地良かったです♪

狛犬の頭に水が溜まって、
まるで河童のようになっていたのが印象的でした。

*****
青渭神社
創建年代は不詳。
光仁年中に創立と伝承がある、
「延喜式神名帳(当時の神社一覧)」に記載されている
多摩八座のうちの一社で古社である。
青渭神は、水神であると考えられる。
例大祭には青渭獅子舞と呼ばれる獅子舞が奉納される。
稲城市東長沼1053
*****
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
稲城市を散策してきました。
大丸用水遊歩道を歩いたのち、訪れたのが、
「青渭神社(あおいじんじゃ)です。

現在の社殿は(昭和49年)に造営された
コンクリート造りであるが、
覆殿内に安置された本殿は17世紀初期の建立と推測されている。
境内は、天気のせいもあるかもしれませんが、
静かで心地良かったです♪

狛犬の頭に水が溜まって、
まるで河童のようになっていたのが印象的でした。

*****
青渭神社
創建年代は不詳。
光仁年中に創立と伝承がある、
「延喜式神名帳(当時の神社一覧)」に記載されている
多摩八座のうちの一社で古社である。
青渭神は、水神であると考えられる。
例大祭には青渭獅子舞と呼ばれる獅子舞が奉納される。
稲城市東長沼1053
*****
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
2013年11月01日
新東京百景~弁天洞窟・威光寺 (稲城市)~
10月26日(土)は、三多摩エンジョイ倶楽部のイベントで、
稲城市を散策してきました。
「青渭神社」の次に訪れたのが、
威光寺にある弁天洞窟です。
横穴式の古墳を明治の初めに堀り広げた洞窟で、
23体の仏像と2匹の蛇が祭られています。
関東屈指の地下霊場であり、
新東京百景にも選出されております。
三多摩エンジョイ倶楽部としては、二度目の訪問になります。
(以前はオプションツアー)
よって私は今回、洞窟内に入るのは止めましたが、
結構低く、勿論中は暗闇。
その中を蝋燭の火で入る事になります。
入場料は300円です。
一度は訪れてみる価値のある、名所ですよ!



弁天洞窟・威光寺 (稲城市)
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
稲城市を散策してきました。
「青渭神社」の次に訪れたのが、
威光寺にある弁天洞窟です。
横穴式の古墳を明治の初めに堀り広げた洞窟で、
23体の仏像と2匹の蛇が祭られています。
関東屈指の地下霊場であり、
新東京百景にも選出されております。
三多摩エンジョイ倶楽部としては、二度目の訪問になります。
(以前はオプションツアー)
よって私は今回、洞窟内に入るのは止めましたが、
結構低く、勿論中は暗闇。
その中を蝋燭の火で入る事になります。
入場料は300円です。
一度は訪れてみる価値のある、名所ですよ!



弁天洞窟・威光寺 (稲城市)
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
2013年11月01日
静かで趣ある古寺~妙覚寺(稲城市)~
10月26日(土)は、三多摩エンジョイ倶楽部のイベントで、
稲城市を散策してきました。
この参道の石段は、趣のある雰囲気でした。

こちらが本堂です。

この妙覚寺には、見事な板碑がありました。

左の写真は正面から、
右の写真は横から撮りました。
右の写真、分かりますかねぇ~。
その薄さ、約2cmでした!
*****
板碑は青石塔婆ともよばれ、
先祖の追善供養や、
自己の極楽浄土を祈る逆修供養のために
立てられた供養塔である。
この板碑は、室町時代の中頃、
秋の彼岸の中日に、道秀という人が、
逆修供養のために建てたもので、
保存状態良好な板碑である。
*****
*****
妙覚寺
開山は室町時代後期。
足利第12代将軍・足利義晴候が開基となり創建。
鎌倉・建長寺の末寺として建立され、
現在の建物は、1796年に再建したもの。
稲城市矢野口2454
*****
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
稲城市を散策してきました。
この参道の石段は、趣のある雰囲気でした。

こちらが本堂です。

この妙覚寺には、見事な板碑がありました。

左の写真は正面から、
右の写真は横から撮りました。
右の写真、分かりますかねぇ~。
その薄さ、約2cmでした!
*****
板碑は青石塔婆ともよばれ、
先祖の追善供養や、
自己の極楽浄土を祈る逆修供養のために
立てられた供養塔である。
この板碑は、室町時代の中頃、
秋の彼岸の中日に、道秀という人が、
逆修供養のために建てたもので、
保存状態良好な板碑である。
*****
*****
妙覚寺
開山は室町時代後期。
足利第12代将軍・足利義晴候が開基となり創建。
鎌倉・建長寺の末寺として建立され、
現在の建物は、1796年に再建したもの。
稲城市矢野口2454
*****
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
2013年11月01日
ただただ合掌!~ありがた山墓石群(稲城市)~
10月26日(土)は、三多摩エンジョイ倶楽部のイベントで、
稲城市を散策してきました。
「妙覚寺」のわき道を通り、その先にある南山山腹にあるのが、
「ありがた山墓石群」です。

*****
関東大震災後、震災の傷も癒えつつあった、
昭和15年から18年頃にかけてのこと。
都内駒込周辺の廃寺などに放置されていた無縁仏や石仏・石像を、
「日徳海」という宗教団体の人々が1つ1つこの地に運んで、
ありがた山の墓石群が誕生しました。
当時の妙覚寺の住職の好意により、
妙覚寺の上の山林が供養の場所になりました。
その石仏・石像の数は4,000体を超えるといわれています。
無縁仏の墓石を運ぶときに、
「ありがたや、ありがたや」と唱えたことから、
ありがた山の名称が生まれたと伝えられています。
*****
ただただ合掌!
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』
稲城市を散策してきました。
「妙覚寺」のわき道を通り、その先にある南山山腹にあるのが、
「ありがた山墓石群」です。

*****
関東大震災後、震災の傷も癒えつつあった、
昭和15年から18年頃にかけてのこと。
都内駒込周辺の廃寺などに放置されていた無縁仏や石仏・石像を、
「日徳海」という宗教団体の人々が1つ1つこの地に運んで、
ありがた山の墓石群が誕生しました。
当時の妙覚寺の住職の好意により、
妙覚寺の上の山林が供養の場所になりました。
その石仏・石像の数は4,000体を超えるといわれています。
無縁仏の墓石を運ぶときに、
「ありがたや、ありがたや」と唱えたことから、
ありがた山の名称が生まれたと伝えられています。
*****
ただただ合掌!
☆★
多摩地区を散策などで愉しむサークル『三多摩エンジョイ倶楽部』










